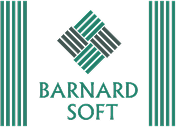はじめまして。7月から中途で入社した者です。
先日、日本経済新聞で長年書評をされていた中沢孝夫という方が出版した
その名もずばり『本を読む』というタイトルの書籍を購読したので
今回、その感想を少し書かせていただきます。
背景として、私自身本を読む習慣はあまり無く、映像化作品の原作小説を読む程度。
(ハリーポッターシリーズ、冲方 丁、米澤穂信、支倉凍砂etc.・・アニメ寄り)
技術の分野で参考になるような本を探していたところ、この本が目についた次第です。
さて『本を読む』は、
・著者の人生・来歴紹介
・著者が感銘・影響を受けた本の紹介
・「本を読むこと」はどのような利点があるのか
・書評という仕事について
を書かれています。
※余談:気になって本書で言及している本タイトルを逐一メモりましたが、計90冊にものぼっていました!さすが!
また、本書の中でビジネスパーソン向けの新刊本(2018年~出版)を紹介しているので、参考にしたい方は書店でパラ読みしてもいいかもしれません
この本を読んで含蓄があると感じた言葉は2つ。
“新しく物事を考えるためにはリベラルアーツが必要である。”
当たり前ですが新技術とは基本的に既存の技術・知識を組み合わせてできるもので、
それを生み出すためには自分の中に確かな土壌を持っている必要がある という風に捉えました。
新技術という目線でなくとも、別の観点・視座を高く持てれば
コミュニケーションや行動を起こすときなど、何かと役に立ちそうですね。
※リベラルアーツ:技術的・専門的な知識と区別されて教えられる幅広い教養
“ある程度の歳になると、自分が心地よいと思える意見のみを聞くという姿勢になってしまうのである。
(中略)他者の意見を知るための素材として本を読む、あるいはそのための選択肢としての書評を読む。”
自分を見直すきっかけとして本を読む、という選択肢がある時点で文化人だなと感じます・・
本は一方的にこちらに情報(意見)を送り込んでくるので、自分だったら納得できる材料を提示されてない限り読むのをやめてます。
こちらあとがきを除いて150ページ程度の書籍ですが、これから本を読む上でのヒントになりました。そこそこ良い買い物でした。
これを読んだ方にも、なにかいいきっかけになればと思います。
P.S.
妻が学生の頃小説をそこそこ読んでいたようで、「エンジニアならこれ面白いかもね」と、
上記の本を購入する際に2冊お勧めされました。近いうちに読もうと思っています。
→早瀬耕 著 『グリフォンズ・ガーデン』『プラネタリウムの外側』
(担当:水雲心太)